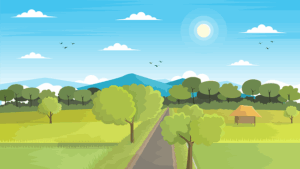【徹底解説】相続土地国庫帰属制度で帰属できる土地・できない土地の違い
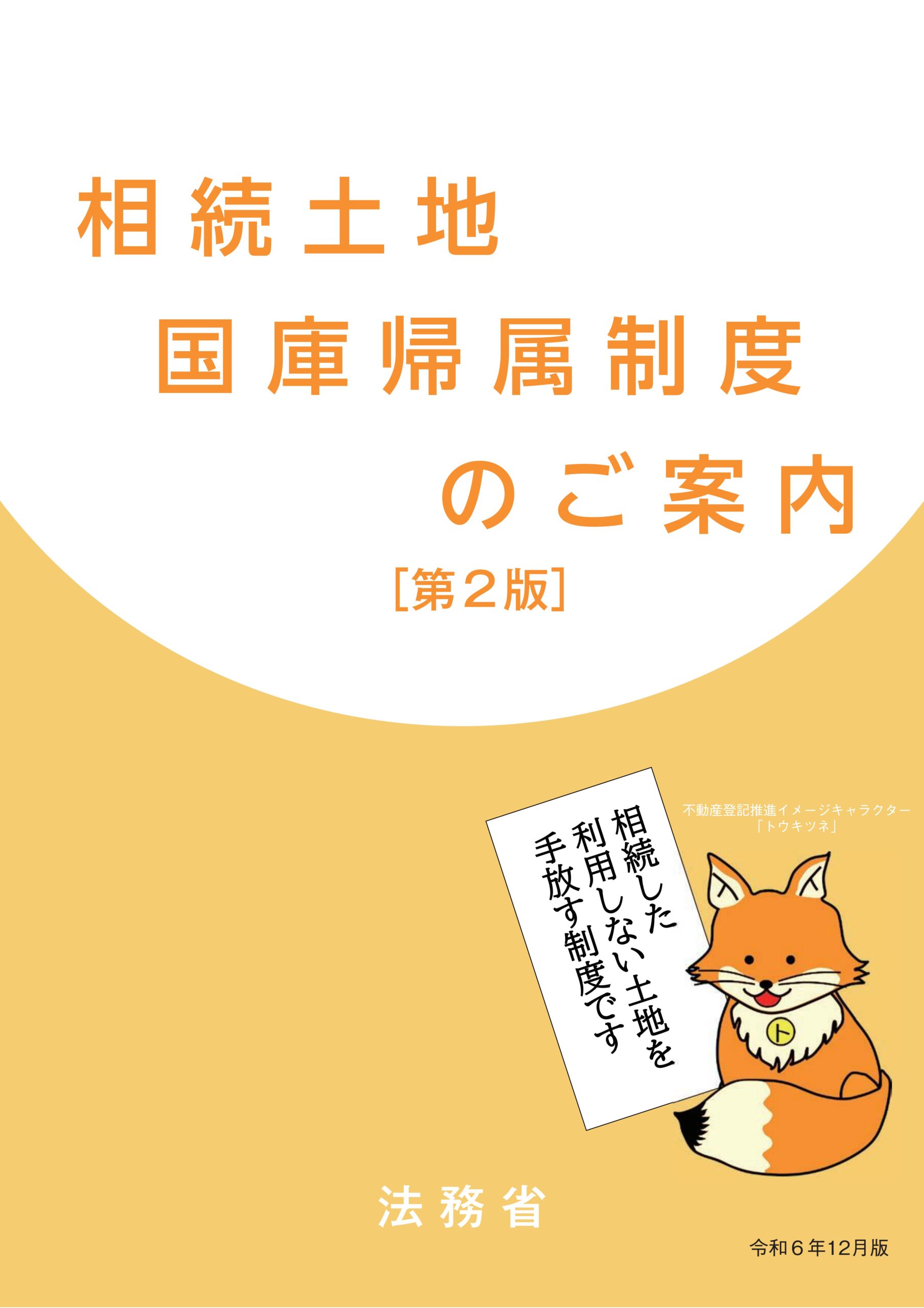
【徹底解説】帰属できる土地 vs. 帰属できない土地|相続土地国庫帰属制度
土地家屋調査士が“帰属可能”か“対象外”かの境界を具体例で詳解。申請前に必読です!
✅ 注意事項:帰属の可否はあくまで「原則」であり、最終判断は法務局
本記事で紹介した「帰属できる土地」「帰属できない土地」の分類は、制度上の原則に基づく一般的な目安です。
実際の申請においては、土地の状況・権利関係・現地調査結果などを踏まえ、法務局による個別判断が行われます。
そのため、原則上「帰属可能」と思われる土地でも、追加資料の提出や整備が求められる場合があります。
また「対象外」とされる土地でも、条件を満たすことで申請可能となるケースもあります。
▶ ご自身の土地が制度の対象かどうかを正確に判断するには、事前の現地調査・測量・法務局との確認が不可欠です。
土地家屋調査士として、制度の運用実績に基づいたアドバイスとサポートを提供しておりますので、お気軽にご相談ください。
1. 国への帰属ができる土地の条件
次の全てを満たす土地が「帰属可能」となります。
| 条件 | 解説 |
|---|---|
| 相続または遺贈で取得 | 生前贈与や購入では対象外。相続発生後に取得した土地のみ。 |
| 遠隔地かつ利用予定なし | 自己利用・賃貸・売却予定がなく、二次利用も見込めない土地。 |
| 管理負担が大きい | 雑草・倒木・崖崩れなど常時管理が必要で、維持コストが過大。 |
| 共有名義は全員同意 | 共有地の場合、原則全共有者の申請が揃っていること。 |
| 耕作放棄地・山林 | 過去に農作物があったが現在使われておらず、整備に高コスト。 |
| 雑種地 | 資材置場や廃車置き場として放置され、再利用プランがない土地。 |
| 小規模宅地(売却見込なし) | 住宅が取り壊され更地状態、売却や活用予定がない宅地。 |
2. 帰属対象外となる土地の条件
以下に該当する土地は、制度の対象外となり帰属申請ができません。
| 条件 | 理由・注意点 |
|---|---|
| 建物・工作物が残存 | 建物や車両、動産等が地上にあると対象外。申請前に撤去が必要。 |
| 道路・公共用地 | 道路用地、上下水道用地など公共管理が前提の土地。 |
| 境界未確定 | 境界標が未設置、測量図が未作成の土地は申請不可。 |
| 災害リスクが高い | 崖崩れ危険地、土砂災害警戒区域など。 |
| 権利関係に問題 | 抵当権・地上権・賃借権などが設定されている土地。 |
| 農地(耕作継続中) | 現に農業用として利用中の土地は対象外。 |
| 国立公園内の土地 | 公園管理者の許可が必要な自然保護区域。 |
| 国や自治体が既に管理 | 公園、緑地、河川敷など既に公共管理下にある土地。 |
3. ケーススタディ:分かりやすい具体例
- 例1:山林(売却見込なし・年1回草刈必須)→ 帰属可能
- 例2:小規模宅地(敷地内小屋あり)→ 整備・撤去後に再申請
- 例3:市街化区域の宅地(再開発計画あり)→ 売却・寄付検討
- 例4:耕作放棄田(雑草繁茂・遠隔地)→ 帰属可能
- 例5:共有山林(共有者全員同意済)→ 帰属可能
- 例6:市街地駐車場跡地(アスファルト撤去要)→ 撤去後に申請可
- 例7:河川敷(河川管理者の管理下)→ 対象外
- 例8:畑(現在耕作中)→ 対象外
- 例9:国立公園境界内の雑種地(保護区域内)→ 対象外
各事例の測量・境界確認ポイントは異なります。詳しくはご相談ください。
4. まとめ&無料相談のご案内
本記事で「帰属可能な土地」と「対象外の土地」を整理しました。
「うちの土地はどちらだろう?」とお悩みの方は、ぜひ無料相談をご利用ください。
土地家屋調査士 淵名事務所が、相続国庫土地帰属制度の実績がある司法書士と協力し、現地調査から申請までトータルサポートします。
人気ブログランキング